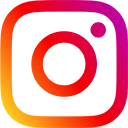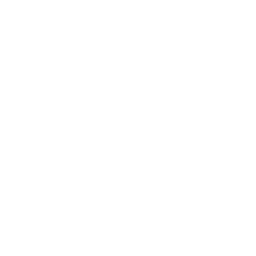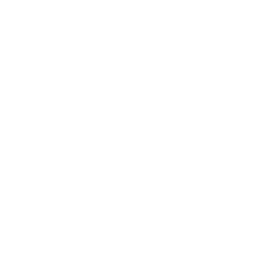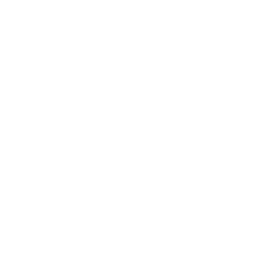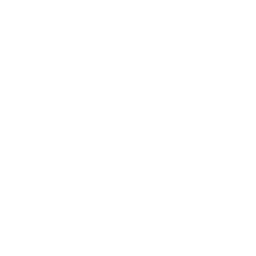ホタルジャコとは?愛媛県南予のじゃこ天を支える“幻の高級魚”

この記事では、南予地方を代表する名産品「じゃこ天」を支える魅力的な魚、ホタルジャコについて詳しく紹介します。ホタルジャコはアカムツに近い味わい豊かな希少魚で、その旨味がじゃこ天に深みとコクをもたらします。この魚は地元では非常に大切にされ、ほとんどが地域内で消費されるため、知る人ぞ知る“幻の高級魚”とも称されています。記事では、ホタルジャコの分類や特徴、アカムツとの共通点を通して、その旨味と食感について深く掘り下げています。また、市場に出回らない理由や地元での呼び名についても紹介します。「じゃこ天」の歴史や、ホタルジャコをすり身にした時にしか出せない独特の味わいも探ります。この奥深い食文化を理解することで、ホタルジャコの魅力をさらに感じていただけます。この記事を通じて、ホタルジャコの知られざる一面を楽しんでください。
ホタルジャコとは?アカムツに近い“旨味たっぷり”の希少魚
ホタルジャコは日本の沿岸で採れる希少な魚で、その深い旨味と上品な風味から、一度食べると忘れられない魅力があります。この魚は、アカムツとも関係が深く、本格的な料理を楽しむ方にとっては垂涎の対象となることもしばしばです。そのため、市場にはあまり出回らず、ひっそりと地元の市場でその姿を現します。
ホタルジャコの分類と見た目の特徴
ホタルジャコは、スズキ目ホタルジャコ科に分類される小型魚です。体長は10〜15cmほどで、細長い体に大きな目、赤みを帯びた体色が特徴です。その姿からは想像しにくいかもしれませんが、アカムツ(通称のどぐろ)と近縁で、味の良さでも知られています。
この魚の名にある「ホタル」は、実際に光る性質を持っていることに由来します。ホタルジャコの腹部には発光器があり、ここに共生する発光バクテリアによって発光します。海底でほのかに光る様子が、まるでホタルのように見えることから、「ホタルジャコ」と呼ばれるようになったと考えられています。
アカムツとの関係性とは?味や食感の共通点
アカムツはスズキ目ホタルジャコ科アカムツ属に属しており、ホタルジャコも同じくホタルジャコ科の仲間です。サイズには大きな差があるものの、どちらも深海域に生息し、脂の乗りがよい白身魚として知られています。
ホタルジャコは小型ながらも、アカムツに匹敵するほどの上品な脂と豊かな旨味を持っています。焼いたときの香り立ちや、身からにじみ出る脂の質感が非常に似ており、食通の間では「小さなのどぐろ」と表現されることもあるほどです。
また、ホタルジャコはすり身にして使われることも多く、熱を加えることでさらに甘みとコクが引き立つ点もアカムツとよく似ています。煮ても焼いても揚げても美味しいという点で、非常に汎用性が高い魚であることも共通しています。

地元での呼び名
ホタルジャコは、地元・愛媛県南予地方を中心に親しまれている魚ですが、地域によって呼び名が変わるのも面白いところです。たとえば、愛媛県宇和島市周辺では「ハランボ」という名前で呼ばれています。
ちなみに、ホタルジャコは市場にはあまり出回らない魚で、主に地元で消費されています。そのため、県外では名前すら知られていないことも少なくありません。
地元のスーパーや鮮魚店でも、運が良くなければなかなか見かけることができず、見つけたら“当たり日”という感覚です。
なぜ市場に出回らない?
ホタルジャコという魚の存在は、あまり広く知られていませんが、地元の人々にとっては特別な存在です。この魚はアカムツに近い味わいを持ち、その旨味は一度味わった人の舌を虜にします。しかし、なぜこのホタルジャコが広く市場に出回ることがなく、“知る人ぞ知る魚”となっているのでしょうか。その背景には、地元での消費習慣や特異な市場流通の理由があります。
地元消費が中心で“知る人ぞ知る魚”に
ホタルジャコは、その美味しさにもかかわらず、ほとんど市場に出回ることのない魚です。その理由ははっきりしていて、漁獲量が安定しないうえに、ほとんどが地元で消費されてしまうからです。
特に愛媛県南予地方では、じゃこ天の原料として非常に重宝されており、地元の加工業者が優先的に買い取っていくのが一般的。そのため、県外どころか県内の他地域でもあまり見かけることがない魚です。
さらに、ホタルジャコは小さくて鮮度が落ちやすく、見た目にも地味なため、一般的な鮮魚流通には乗りづらいという事情もあります。冷凍や加工品としてでなければ品質の保持が難しく、その点も市場に流通しない理由の一つです。
結果として、ホタルジャコは地元の人々が昔から当たり前のように食べてきた日常の魚であると同時に、地元を離れるとほとんど知られていない“隠れた存在”になっています。
つまり、ホタルジャコは単なる地域の特産魚というだけでなく、南予の食文化そのものを支える、縁の下の力持ちとも言えるのです。
ホタルジャコは高級魚?
では、ホタルジャコは高級魚として位置づけられているのでしょうか。実は、その希少性と味わいから、地元では高く評価されています。市場に出回らないため価格は一定ではありません。年末など、練り物製品の需要が高まる時期には、ホタルジャコの価格も大きく上昇します。特にじゃこ天やかまぼこなどの原料として重宝されるため、一箱(約14kg)あたりで2万円を超える相場になることも珍しくありません。これは、他の小魚と比較しても高値であり、ホタルジャコがいかに価値ある原料として扱われているかを物語っています。

南予名物「じゃこ天」を支える名脇役
愛媛県の南予地方で特産品として親しまれている「じゃこ天」は、古くから地元の食文化に深く根付いています。その美味しさを裏で支えているのがホタルジャコという希少な魚。この魚は、豊富な旨味とコクが特徴で、地元ではひそかに“名脇役”として愛されています。では、まずこのじゃこ天の歴史をひもといてみましょう。

じゃこ天の歴史
じゃこ天が誕生したのは江戸時代の終わり頃とされています。当時の南予地方は漁業が盛んで、新鮮な魚をすぐに消費するだけでなく保存食として加工する文化が発展していました。じゃこ天は余剰魚を有効活用するために生み出されたもので、小魚をまるごとすり身にして油で揚げるという製法は、人々の知恵と工夫の賜物です。その後、明治時代に入ると、じゃこ天は栄養価が高く保存が利く食品として地元で重宝され始めます。
すり身にしたときのコクと旨味の秘密
ホタルジャコをすり身にすると、その旨味が一層引き立ちます。この魚は、脂肪分が適度に含まれており、焼くことで旨味とともに香ばしい香りが広がります。この風味がじゃこ天に特別なコクと深みを与えているのです。また、ホタルジャコの身は緻密で、すり身に加工する際にその特性が凝縮され、独特の食感が生まれるという特長があります。これが、多くのじゃこ天愛好者を魅了してやまない理由と言えるでしょう。
ほかの魚では出せない“味の深み”とは?
ホタルジャコの魅力は、その独特な旨味の深さにあります。ほかの魚にはない風味の一部は、ホタルジャコが生息する海域の環境にも影響されています。南予の豊かな海で育つこの魚は、潮の流れや水質から影響を受けており、この地ならではの味わいを醸し出すのです。そのため、同じ製法で作ったじゃこ天であっても、ホタルジャコを使用したものは特に味わい深いとされています。この個性的な味は、地元の食通だけでなく、訪れる観光客にも感動を与えるのです。
ホタルジャコは知れば知るほど味わいたくなる魚
ホタルジャコって、最初は名前も聞いたことがないという方が多いかもしれません。でも、その正体を知ると、「そんなに美味しいの?」「じゃこ天に入ってたの!?」と驚かれる方がほとんど。
アカムツに近い旨味を持ちながら、市場にはなかなか出回らない“幻の魚”。だからこそ、地元の人たちが大切に使い続け、じゃこ天や家庭の味として受け継がれてきたのです。
じゃこ天を食べたときの、あのじゅわっと広がる旨味。その背景には、ホタルジャコのような個性豊かな小魚たちの存在があります。すり身にしても、煮付けにしても、唐揚げにしても美味しいホタルジャコは、南予の食文化を知るうえで欠かせない存在です。
もし愛媛・南予を訪れる機会があれば、ぜひ地元のじゃこ天やホタルジャコ料理を味わってみてください。見た目は地味でも、一口食べればきっと、ホタルジャコの魅力にぐっと引き込まれるはずです。
知れば知るほど、味わいたくなる魚。ホタルジャコは、そんな不思議な魅力を持った南予の宝物です。